200年以上続いた鎖国政策を経て1853年に開国を迫られた日本は、外の世界にとって謎に満ちた国であった。 ある意味、今でもそうです。 しかし、思想から衣服に至るまで、西洋のものをいち早く取り入れた日本には、親しみを感じることができる。 神社や相撲など、馴染みのないものであっても、今では「日本」として認識されている。 しかし、日本の作家が自国について語ることは、あまり認識されていない。 ロボットと暮らす家族を描いたドキュメンタリー作家ではなく、作家がその謎を解き明かしてくれるのです。 これらの本は、しばしば語られ、語られ、他者によって推測される日本を代弁している。彼らは、展開されたその歴史、実践されたその文化、生活し、戦ったその社会を代弁しているのである。
村上龍著『コインロッカー・ベイビーズ』
Ryū 村上春樹の物語は、社会の最も暗い部分に光を当てることを決してためらわない。 この1980年の作品では、主人公のキクとハシが遭遇するおぞましい出来事とその全生活が描かれ、その光はさらに増幅された。 1970年代に問題となったコインロッカーに捨てられた「コインロッカー・ベイビー」のふたりは、九州の島に住む子供のいない夫婦のもとに養子に出される。 都市と農村の衰退を背景に、彼らは成長する。 外国人、ホームレス、麻薬の売人、犯罪者など、日本で隠蔽されているあらゆるものが集まる東京の架空の地域 “トキシタウン “に移住し、愛とスーパースターの高みから狂気と殺意まで、シュールな青春ホラーストーリーが繰り広げられる。
村田沙耶香著『コンビニの女』
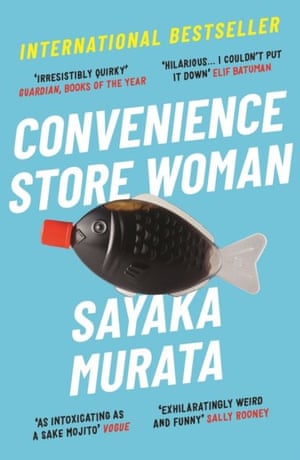
“コンビニとは音の世界 “である。 語り手である恵子さんのコンビニでのアルバイトの息づかいが伝わってくるような冒頭の一節が素晴らしい。 彼女は終始、店の音を教会の鐘に、自分や同僚をある宗教の信者にたとえている。 これは、ローソン、セブンイレブン、ファミリーマートといった日本のコンビニエンスストアの些細な特徴を示すだけでなく、普通であることに対する実存的な挑戦でもある。 社会の一員になろうとコンビニで働くケイコは、「歯車」になるのだが、それだけではない。 サルトルのウェイターがあまりにも「ウェイター的」であるように、コンビニの店員はどうあるべきか、日本社会の縮図を体現しているが、そのことによって、結婚や出産、それにまつわる高慢なカップルといった現実社会から遠ざかっている。
三島由紀夫「海に消えた船乗り」
『蠅の王』であり、『エディプス・コンプレックス』でもある本書は、戦後の苦悩の遠吠えである。 俳優、モデル、映画監督、作家である三島の主人公、信郎は、横浜でシングルマザーの房子と暮らす思春期の少年である。 彼はまた、表面的には「いい子」である同級生たちとニヒルなギャングに属することになるのだが……。 母の寝室の覗き穴を発見するなど、随所でセックスが暗示されているが、信郎がかつて憧れていた房子の新しい恋人、船員の龍二に感じた極度の失望が、栄光を取り戻すための全く残酷な計画の歯車を動かすことになる。 現実の三島は、戦後の日本の状況に失望し、1970年に自らが設立した右翼団体「楯の会」のメンバーとともに東京の軍事基地を襲撃し、駐留軍に演説をしてクーデターを起こそうとした。 歓呼の声を受け、切腹した。
川上弘美著『東京の天気』
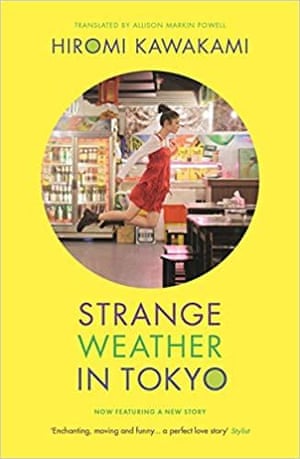
東京人の交流と探求を描いたこの作品は、江戸時代(1603-1858)の浮世、つまり都市生活の急成長に言及し、現代風に穏やかにアレンジしたものである。 居酒屋での外食、桜の季節の花見、そして国民的人気の野球と、川上さんの刹那的な世界。 夏目漱石のベストセラー『こころ』にも通じる「年上と年下」というテーマで、30代の女性が「先生」と呼ぶ年上の男性と関係を深めていく物語が、ほのぼのとした雰囲気で描かれています。
夏目漱石の「吾輩は猫である」

Sōseki の処女作は、日本の明治時代(1868-1912)と西洋思想の不安な取り入れ方を、ある学校の教師の人生を通して風刺しています-彼の愚かさ、友人の輪、彼の時間の使い方などです。 彼は東京の中流階級に属する普通の人間で、近所の子供たちが木の棒で庭にボールを打ち続けるとイライラするような気難しい人物である(この時代、日本には野球が新しく入ってきていたのだ)。 この小説が1905年から2006年にかけて連載されたことを考えれば、なおさらである。 日本語には「私」を表す代名詞が複数あるが、猫は自分自身のことを「わがはい」と言い、当時としても珍しい高貴な表現をしている。 しかし、この本の人気によってワガハイは復活し、現在でも擬人化された架空のキャラクターが使用することはあまりない。
Some Prefer Nettles by Jun’ichiro Tanizaki
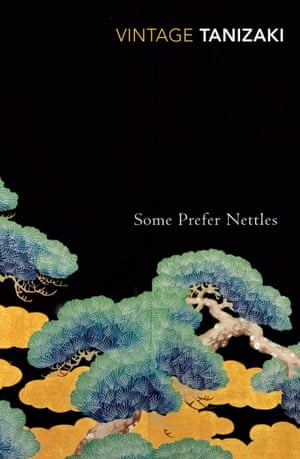
日本の過去への洞察と、日本の特異な西洋化様式を理解する青写真として、谷崎はこの小説で矛盾する利益の網を紡ぎます。 要とその妻美佐子は結婚しているが、幸せとは言えない。 要の義父である「老人」は、離婚は問題外であり、西洋の考え方によって引き起こされた問題に対する西洋の解決策であると考えている。 老人は、夫婦と若い愛人お久に日本的な理想を植え付けようとし、日本が変化する中で伝統を守ろうとする。 しかし、要は西洋のものが大好きだ。 当時のアメリカの映画スターに憧れている。 彼の犬は英語の名前まで持っている。
清少納言の枕草子

メレディス・マッキニーによる2006年の翻訳のおかげか、『枕草子』はまるで今日書かれたかのように自然に読める。 ただし、一条天皇の皇后である藤原定家の侍女によって、990年代から1000年代初頭に書かれたものであることを除いては。 日本の歴史の中でこの時代、平安時代(794-1185)は、貴族にとって、とにかく重要な時代であった。 セイさんの本は、基本的に思いつきで書いた古代のブログのようなものである。 川や市場など、有名な場所や歌にまつわる場所、あるいはその両方をリストアップし、「うらやましいと思う人」「恐ろしい名前のもの」などというタイトルのインデックスを付けて、意見を書いているのである。 しかし、そのほとんどは、夜中の男性の訪問、神社の祭礼、廷臣たちの間で絶え間なく交わされる洒落た詩のやりとりなど、宮廷の世界を覗くための窓となっているのです。
太宰治『女生徒』

太宰は、自伝的作品『もはや人間ではない』(1948)でよく知られているかもしれないが、彼を有名にしたのは、1939年の小説『女生徒』であった。 同名の少女が語るこの作品は、戦前の日本版『ライ麦畑でつかまえて』であり、彼女にとってはすべてが憂鬱で、哀れで、嫌なものである。 “朝は拷問” 語り手は時にアンドロイドのような声で、自分自身や周囲の世界と対立しながらも、出版から81年経った今、彼女の考えは現代に通じるものがある。 マルクス主義者であった太宰が、超国家主義を批判しているのかもしれない。 つまり、誰もが自分の生まれた場所を愛しているのです」
Vibrator by Mari Akasaka

タイトルで敬遠する人もいるかもしれないし、版によってはエレクトリックピンクの表紙があったりなかったりするが、『ヴァイブレータ』は華やかである。 この小説は、主人公の早川玲が近所のコンビニに通い始める、少なくとも少しの間、東京を舞台にしています。 彼女は過食症のフリーランス・ライターで、お酒を飲みすぎる。 その店で偶然出会ったトラック運転手の岡部と、いつもの自堕落な日常から離れ、彼の運転する車に乗り込み、ドライブに出かける。 日本の高速道路は決してきれいではなく、冬景色も皆さんが知っているような繊細な木版画の風景ではありませんが、本書はその両方を最高の平凡さで見せてくれます。玲は見知らぬ人と北の果てまで旅をし、さらに自分の中に入っていくのです。
村上春樹『ハードボイルド・ワンダーランドと世界の終わり』
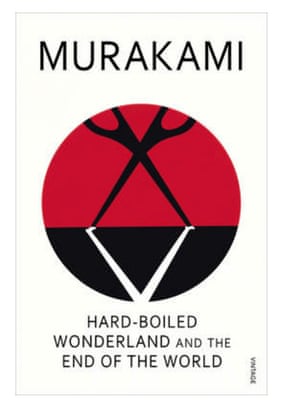
本書の舞台は半分だけ日本である。 というのも、他の章はすべて「世界の終わり」と呼ばれる実在する(あるいは実在しない)場所が舞台となっており、その住人は痛々しいほど無心で、おそらく魂すらないのである。 一方、その間のすべての章は、「ハードボイルド・ワンダーランド」という別の東京が舞台で、そこでは語り手が一種の人間データ処理機械として働いている。 この物語には首をかしげざるを得ない。 名もなき語り手は、この小説の印象的な部分を、最新の河童(日本の民間伝承の水陸両用鬼)がうようよしている怪しげな下水道で過ごし、この秘密の地下迷宮から、青山一丁目駅(全編にわたって名前が挙がっている東京の場所の1つ)に出てくるのです
。